さて、ハリスの言う「幸福の罠」とはどんなものか?「幸福の罠を一言で表せばこういうことだ。私たちは幸福になるために嫌な感情を排除しようとする。だが排除すればするほど、感情は再生産される」(p.38)ような事態のこと。つまり心理的に悪循環を作っている、というのだ。「不快な思考や感情を追い払う努力が人生を余計に悪くしている」(p.29)という。
具体例としては、例えばこんな場合。「ジョセフは人に拒否されるのが怖いため、社交の場を恐れている。この不安から逃れようと、彼は付き合いの場を極力避ける。パーティーの誘いを断り、友人関係も持たない。同居人はなく、毎晩一人で過ごす。その結果、たまに人づきあいする時はこれ以上ないほど不安になる。普段人と触れ合う練習をしてないからだ。さらに、友人なし、人づきあいなしの生活のせいで、彼は世間から拒絶されていると感じている。そしてそれこそが、彼が一番恐れていることなのだ」(p.30)。
「ダニエルは少々太り気味なのを気に病んでおり、気分を盛り上げるためにいつもチョコレートを食べていた。しばらくの間はそれで気が晴れる。だが次の瞬間、摂取したカロリーとそれによって体重が増えることを思い、かつてないほど惨めな気分になるのだった」(p.30)。
誰もが多かれ少なかれ思い当たるところがあるでしょう。「ジョセフ」の例なんかは、元ひきの私としては、ほぼ自分のことかと(笑)。
このように、不快な思考や感情を追い払ったり、避けたり逃げたりすることを、ハリスは「コントロール戦略」と呼んでいる。そしてコントロールの仕方には二種類あるという。「逃走」と「闘争」の二種類。
逃走戦略は、ジョセフの例とか、一日中TVに逃避するとか、酒に逃げるとか、そういった方法。闘争戦略の方は、無理やり不安や不快な思考を抑圧しようとしたり、心の中で思考に反論したりする方法。
ハリスは、コントロール戦略が、いつでも常にダメなものだとは言っていない。それが適度に、うまくいくときだけ使えるのであれば問題はない、という。つまりそれが「悪循環」を生み出さない程度に、うまく使わているのであれば、それは「幸福の罠」にはならない。
しかし往々にして、コントロール戦略は、過剰に、不適切に、そして私たちが本当に価値のあると思う行動をとることを邪魔する方向で働いてしまう、というのだ。
効果があらわれないにもかかわらず、私たちはコントロール戦略を使い続けてしまう。そうすると、コントロール戦略の、三つの大きな問題があらわれるという。
1. 多くの時間とエネルギーを使う割に、長期的には効果が薄い。
2. 追いやった思考・感情はすぐに戻ってきてしまうため、自分はおろかで不完全で弱いと感じてしまう。
3. 短期的に不快感を封じ込める戦略の多くは、長期的には生活の質を損なう。
(p.37)
ここでエクササイズが用意されている。「私が最も取り除きたい感情・思考は……だ」という文章の「……」を埋め、そしてさらに、これらを回避するために行ったことをすべて書き出そう、というものだ。
この問いは私にとっては、「あなたはなぜひきこもったのか?」という問いとほとんど同じです。で、それはまあ私にとっては大変な問いだ。それこそ人生かかってる、というか。自分の人生全部振り返る問い、というか。
うー…、ん。人や社会が怖かった…。のだが、人や社会の何が怖かったのだろうか?それらと関わることで、自分の中で発生する、どんな思考や感情から逃げたかったのだろうか?
…、と、この問いについて考えていて、一応の答えは出ました。私は、他人からいじめられたりいじられたり、軽い存在や「下の」存在として扱われるのがつらかったのだ、ということを思い出した。そして、他人からのそういう評価は、内面化されていってしまう。つまり自分でも、自分のことを「低く」自己認識するようになる。「俺なんてクソだ」と。
で、やっぱりそれはつらいことだ。自分で自分のことを「クソ」だとは思いたくない。そこでそれこそまっとうな努力ができればよかった。学校での勉強を頑張る。部活で成果を残す。あるいはそのどちらでもなく、人間関係の中で「面白い」キャラでポジションを獲得し他者のリスペクトを得る。
何もできなかった。いや、お笑いは好きだったし、小さいグループの中で少しでも「面白い」人間であろうとは努力していた気はする。しかしうまくいかなかったし、何よりもどんどん疲弊していった。なぜ自分は「ありのまま」で存在することが許されない(と思い込んでいた)のか、という理不尽さに怒りや悲しみを感じたりしていた。
そこで、人間関係から撤退した。いわば、「不戦勝」を狙う戦略というか。いや、「勝ち」ではないんだけど、少なくとも「負けない」戦略というか。人間関係の中に出ると常に負けるから。
で、どうなったか?ハリス本にある通り、私は人生をだいぶ制限し、多くの時間と可能性を失うことになってしまった。
このエクササイズを行うことによって、「めまいがして頭が混乱し、気分が悪くなったかもしれない」(p.39)とハリスは書く。まさにしかり、だ。自分の人生の、見たくなかった部分に直面させられる感じでくらくらしてくる…。どんだけ私は人生で大事なものを失ってしまったのか…。時間、お金、可能性…。そして俺の人生はもう「詰んでいる」のではないか…。俺の人生は「もう終わっている」のだろうか…。もう50前のおじさんだとはいえ、決して短いとまでは言えない後半生を、ただ惨めな、苦しい時間として、死ぬまで耐えるだけなのか…。
しかしまあ、ここからスタートするしかないのだろう。ハリスも、「自己認識を高めるのが最初のステップだ」(p.41)と言っている。そして確かに、これは大事な「自己認識」だ。ごまかさずに見つめよう。50前のおじさんになってもなお、私は人間関係の中で苦しんでいる。他人からの評価におびえて暮らしている。昔のようにひきこもってはいないが、別に自信がついたわけではない。いまだに職場の人間関係の中で、「俺はクソだ」とか「俺は無能だ」といった物語に苦しめられている。他人の目線や態度から、「お前はクソだ」とか「お前は無能だ」とか「お前はダメ人間だ」とった無言のメッセージを、(私の方が勝手に、だとは思うが)受け取ってしまうのだ。そしてそれを否定しようと躍起になる…、と言って、具体的に何をやっているのだろうか…。可能な限りは人と関わらない、という「逃避」戦略。自分にもできる仕事であれば、うまくこなして他人からの高い評価を獲得しようとする。これは「闘争」戦略なのだろうか?まあいずれにせよ、まさにコントロール戦略だ。
ハリスはこうも言う。「この本を読んだだけでは人生は変わらない。行動を起こさなければいけないのだ。この本はインドの旅行ガイドのようなものだ。読み終わったとき、訪れたくなった場所がたくさんあるだろう。だがあなたはまだそこに行ってはいない。インドを真に体験するためには決然と立ち上がり、出発しなければいけない。本書を読んであれこれ考えるだけでも、読み終わったとき、豊かで満ち足りた、意味ある人生を創造する方法が、身についているはずだ。しかし、あなたはまだそうした人生を生きてはいない。人生をより良くするためには、本書で述べる練習や提案を実行しなければいけない」(p.47)。
ということで、具体的なエクササイズ、具体的な行動は何ができるのか、についても書いていきます。

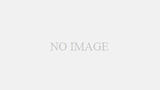
コメント