さて、いよいよ最終章です。第5章「心の認識」です。「認識」という側面から心に迫っていきたいと思います。
心の「認識」といったとき、二つあるでしょう。つまり「他者の心の認識」と「自分の心の認識」です。
① 他我認識
まず、「他人の心」とはそもそも認識できるのでしょうか?よく哲学では「他者問題」なんて言いますね。つまり、デカルトのやったような徹底的な懐疑をするならば、そしてこれまたデカルト的に心身二元論を取り、「心」というものを自分だけがアクセスできる「意識」と定義するのならば、そもそもの他人の心の存在自体疑いうる、という話ですね。目に見えるのは他人の身体だけで、心のないロボットやゾンビかもしれん、ってやつですね。
しかし金杉さんの立場は、「他人の心の認識は可能だ」という立場です。私たちはおおむね問題なくコミュニケーションをとっているでしょう。例えば誰かに、「水ない?」と聞かれたら、「冷蔵庫にミネラルウォーターがあるよ」と答えたり、あるいは無言で自分でそれをとってきて相手の前においてあげたりします。
この事例において私は、相手の言動から「この人は水を飲みたいのだな」と考え、彼の欲求を満たしてあげようと行動したわけです。これは十分、「認識」と呼ばれるに値する事態ではないでしょうか?
確かにここにおいて、先のデカルト的な「他者問題」はあるかもしれませんし、他者の心の理解を間違える、ということもあります。先の事例で言えば、水を持っていった時に、「いやごめん、手を洗いたかったんだ」と言われれば、それは私が彼の言葉の解釈を間違ったわけです。
つまり、「他者の心の認識」は行われているが、しかしそれは、「自分の心を即座に知れる」というのと同じように知れるわけではない、ということです。しかしながら、「他者認識は不可能だ」とか「他者の心など存在しない」とまで主張するのならば、それは極論だ、と金杉さんは考えるのだと思います。
さて、では、「他者認識」とはどのようにして行われているのでしょうか?ここでも金杉さんは、段階に分けて論じていきます。立場は三つ。1.類推説。2.行動主義。3.解釈主義、の三つです。そしてそれぞれ、問題点が指摘され、金杉さんは三つ目の解釈主義に対して好意的です。では、一つずつ考えていきましょう。
1.類推説
二元論的な枠組みで考えても、ある種の他者認識は考えられます。それが「類推説」です。二元論的に考えれば、本当に知っているのは自分の心だけです。そして他人に関しては、他人の身体しか見えていないわけです。
しかし例えばタクシーを止める時に手を挙げる、といった経験を通して、「タクシーを止めたい」という自分の欲求と、「手を挙げる」という身体行動の間の相関関係を学んでいき、かつだれか他人の「手を挙げる」という目に見える身体行動から、彼の心の中を、自分の相関関係を当てはめることによってその存在を「類推する」というわけです。
しかしこの説は成り立っているでしょうか?一般的に言って、一つの事例だけから、その事態が一般的に成り立っている、とは主張できないものです。ここで知っていると言っていい事例は自分のそれ一つだけです。もし自分の事例に当てはまることであるならば、他人の心にも当てはまるはずだ、と言っていいのであれば、「私が鰻好きであることを根拠にして、すべての人が鰻好きであると結論してもよいことになってしまう」(p.171)。
他人にも自分と同じ、心と身体行動の相関関係が成立していることを二元論者は知る必要があるが、それは二元論の定義上、不可能なことなのです。
2.行動主義
「行動主義」と呼ばれる考え方は、類推説とは別のルートで、他者の心の認識を確保しようとする。
そもそも、「心」というものを、物理的な身体の内奥(?)に住まう私秘的な(私だけにアクセスできるような)実体、とは考えずに、目に見える身体行動とつなげて考えてみてはどうか?「たとえば、痛みの感覚は、痛みの振る舞いと切り離すことのできない結びつきを持っているのではないか」(p.173)。行動主義は、「心にとって行動との結びつきは本質的なものである」(p.173)と考え、「傾向性」という概念によって、この結びつきを説明しています。
例えば、「壊れやすさ」とか「水溶性」といったものが「傾向性」の具体例です。そして「壊れやすさとは、実際に壊れているということでも、また、壊れる前の状態でもない。それは、衝撃が加えられれば壊れる、という条件的な性質である。同様に、水溶性とは、実際に水に溶けているということでも、水に溶ける前の状態でもない。それは、水に入れられれば溶ける、という条件的な性質にほかならない。このように、傾向性とは、ある現象Pやそれを引き起こした原因の状態のように、現に成立している状態ではなく、ある条件が成立するとPが生じるという条件的な性質ないし状態のことである」(p.174-175)。
行動主義によれば、そもそも「心」とは、特定の条件が成立するならば特定の行動が生じがちであるという、「行動傾向」のことなのである。
そう考えるのであれば、二元論的な「他我問題」には悩まされないことになります。というのも、それはそもそも心を自分にしかアクセスできない目に見えない実体とするのではなく、目に見える行動と結びつけて考えるからです。
3.解釈主義(あるいは全体論的行動主義)
行動主義に対する金杉さんの不満は、それが個々の心の状態を単独で行動と結びつけるところです。例えば先の事例では、「タクシーに乗りたい」という欲求が、「手を挙げる」という行動に結びつけられたわけです。
しかしこれは、現実の描写として正確でしょうか?何か抽象的な、部分の切り取りではないか?より厳密に描写しようとするならば、そこには言及すべき「心の状態」は他にいくらでもあるでしょう。例えば、「手を挙げればタクシーは止まるものだ」という信念がそもそもなければ、彼は手を挙げなかっただろうし、さらにそもそも論で言えば、「あの四つのタイヤを持つ大きい箱は「車」というものであり、特にあのタイプの車は個人的な乗用車ではなく「タクシー」という…(以下略)」といったような「知識」があることも前提でしょう。
となると、心の状態が個別に特定の行動に結びついているのではなく、複数の心の状態の「全体」こそが、ある特定の行動への「傾向性」を持つ、と考えた方がよさそうです。
そしてそれはつまり、先に紹介した、「解釈主義」の立場となるでしょう。
② 自己認識
さて、では次には「自己知」について見ていきましょう。
「自己知」は、「他者認識」とは違う、ある特徴を持ちます。それは、1.不可謬性、2.自己告知性、3.直接性、です。
まず、1.不可謬性についてです。自分の心の状態に関しては、例えば「感覚」が典型的ですが、「感じ間違い」はあり得ないか、少なくともかなり少ない例外的な状況、と言えるのではないでしょうか?例えば「仮病」や「幻覚」。子供が学校に行くのがつらく、「おなかが痛い」と訴えてきたとしましょう。身体医学的には、例えば消化器官における異常が認められない場合でも、それを「仮病」だとして退けることはできないのではないでしょうか?やはりそれは精神的なことを原因としてではあれ、やはり「痛み」は痛むのです。これは子供の事例を聞く側ではなく、自分自身が「痛い」と感じる側で考えれば分るでしょう。病院に行き、「何もないですよ」と言われようが、「痛みの感覚」は厳然と存在し、「痛みそのもの」の存在自体は否定しようがないでしょう。
「幻覚」の事例においても、それが正常な「知覚」と区別されるのは、それの「客観的な」存在論的身分に関してでしょう。「存在論的身分」って、言葉が大袈裟ですが(笑)。要は、他者との認識のすり合わせや、その知覚の対象が世界そのものにおいても成立しているのか、という段階において改めて問題になるような事柄です。当人に見えている「像」としての「幻覚」像が、当人にとっては見えている、つまり存在している、としなければ、そもそも「幻覚は実際に存在するのか?」という問い自体も立てられないでしょう。当人にとっては幻覚像は存在する、というのは大前提なわけです。これも先の仮病の事例と同様、幻覚を見ている当事者側に立てば、すぐに理解できるでしょう。
以上が、自己知というものが持つ「不可謬性」の説明です。
二つ目の、「自己告知性」はつまり「自己意識」の話です。
これまた「いつも必ず」とは言えないにせよ、おおむね、私たちは自らの心の状態について「自覚」を持つでしょう。これは単純な話で、例えば「カレーを食べたい」と思っているときは自分でもそれを知っている、ということです。当たり前すぎて何かかえって深淵な禅問答をしているみたいですが(笑)、これは端的な事実の指摘です。
もちろん、例えば誰かに対する愛情や憎しみを、しばらく自覚していなくて、ある瞬間に急に自覚する、といった事例は考えられます。とはいえ、そちらの方が例外的で、おおむね「自己告知性」が成立している、という事実は動かないものと思われます。
三つめは「直接性」ですね。他人の心は、認識できるにしても、例えば「手を挙げる」という目に見える身体的行動を、「彼はタクシーを止めようとして、手を挙げたのだな」と「解釈」する、という形で行われます。つまりそれはある種の「推論」を経た「間接的」な知ではあります。
それに対し、例えば同じ例を使うならば、自分が「タクシーを止めたい」と思っている、という事実は、鏡に映った「手を挙げている」自分の姿を目視してそこから推論するわけじゃないですよね。これまた、改めて記述してみると当たり前すぎることの言語化で妙な言葉遣いになってしまいますが(笑)、要はこれも「端的な事実」と呼ぶべき様な事柄ですよね。
で、以上のような特徴を、どのように説明するか。それについて考えてみましょう。それを通して、「心とは何か」という問いに対する寄与が得られるかもしれません。
この自己知の特徴を説明するための道具立てとして、伝統的によく利用されてきたのが「内観」という概念です。読んで字のごとく、(心の)「内」を「観る」ということです。
「観る」という比喩で言われていることから、これは「知覚モデル」と呼ばれます。(身体の?)中にある心の「内」を観る、という言い方からもわかるとおり、この知覚モデルは、二元論と相性の良い考え方です。
二元論的は、「心」という領域を「物質的」な領域から区別します。そして、外的な「客観的」な知覚においては、距離を置いて対象に接するため、その距離に応じて、「見間違い」は存在する。それに対しそもそも「空間的規定」自体を持たない、例えば感覚や感情は、直接体感的に(主観的に)知られ(つまり直接性を持つ)、間違いようもない(つまり不可謬性を持つ)、と。
しかし金杉さんによれば、この説明は満足できるものではないという。そもそも「二元論」には問題が多すぎる。特にこの章で取り上げた「他我問題」を発生させる点は決定的だと言います。ほかにイカにメリットがあるにしても、二元論をとることによる失うものが多すぎる、とのことです。
そしてそのことをわきにおいても、そもそも先の「説明」は本当には説明にはなっていない、と言います。というのも、「物質的なもの」から区別された「心理的なもの」という「定義」それ自体をもって、知の直接性や不可謬性の「説明」にとって変えようとしている、というのです。
物質ならぬ心というものは、あるいは意識は直接主観的に自己意識的に知られる、というのを「事実」として言っても、「なぜそうなのか?」の説明ではない、というわけです。
さてしかし、金杉さんにおいても、十分な説明はいまだ与えられていない、という結論にならざるを得ないそうです。これはもうまたもや「入門書」の範囲を超える、と。むしろ読者が宿題として、絶賛議論中の最前線に出ていくしかなさそうです。

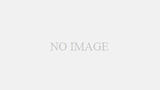
コメント