この章のテーマは「合理性」です。この本でずっと検討されている有力な立場、「機能主義」との関係で「合理性」が論じられています。ではでは、始めましょう。
機能主義のおさらい。心の状態、例えば「欲求」とか「信念」は、ある行為という結果を生み出す「機能」として定義される。例えば「カレーを食べたい」という「欲求」と、「あそこにあるお店はカレー屋だ」という「信念」が原因となって、「カレー屋に入る」という行為が引き起こされる、というような。
で、さらにそれぞれの心の状態は、脳状態によって実現される、と考えます。
前章「心の志向性」で取り上げられたように、信念や欲求といった「命題的態度」は「構文論的構造」を持ちます。つまり、(言語で言えば「語」のような)「文脈独立性」のある構成要素が、(言語であれば「文法」のような)「構成規則」にしたがって組み合わされるような「構造」のことですね。
で、機能主義によれば、構文論的構造を持つ心の状態(たとえば信念や欲求)がそれの持つ機能として定義されるところの脳状態も、同じく構文論的構造を持っているはずです。
しかしながら、現代の神経生理学の成果によれば、否定的な結論になるようです。つまり脳には構文論的構造が見いだされない。
脳は諸ニューロンによる、ニューラルネットワークによって働くのですが、そこにおいて、「文脈独立性」のある要素は見られず、むしろ全体として協同するものなのだそうです。
さて、ここでどう考えるべきでしょうか?
そもそも「命題的態度」とは何か?それは、目に見える身体的行動を、因果的に「説明」する段階で現れる、目に見えない「心」の状態というものを表現する、「理論的存在」なのではないか?そして、その「理論的存在」は、「フロギストン」や「エーテル」のようにかつてはその実在が想定されたものの今はその存在が否定されるべきような、歴史的に誤りが確定した「理論的存在」なのではないか、と考える道がまずあります。この立場は「消去主義」と呼ばれています。
確かに科学の歴史上、「フロギストン」という、「燃焼現象」を説明するための「理論的存在」が立てられていたことがあるそうです。しかし酸素の燃焼によって説明がなされるようになって、「フロギストン」はお役御免になった、と。
しかしながら本当に、私たちの心に関する「民間心理学」及びそれが想定する「命題的態度」はフロギストンと同種のものなのでしょうか?
消去するには及ばない、それらを救い出すことはできる、と考える立場が次に紹介する「解釈主義」です。
消去主義は、そもそも論として「常識心理学」をどんなものとして考えているのか、というと、「行為の因果的説明」のための理論としてなのである。どういうことか。ある行為を説明する際に、その原因にさかのぼってそれに言及することによって、「それを説明した」と考える、ということです。
つまり、「カレー屋に入る」という行為は、「カレーが食べたい」という信念で説明されるわけです。そしてさらに、「物的一元論」であれば、なるべく非物質的な「心」という概念に訴えずに、説明したい。そうなると、それら「信念」も結局は「脳の一状態」である、とすれば、きれいに物質的な世界の因果関係だけに言及すれば、人の行為は説明できるわけです。
で、しかしながら、心の少なくとも一部である、「命題的態度」は、脳状態とは一対一対応はしてなさそうだ、というのが先の結論だったわけです。そこで、因果的な存在としての命題的な態度も、実は存在しない!と考えるのが消去主義なわけだけれども、いくらなんでも私たちの常識とかけ離れてしまわないだろうか?「カレー屋に入りたい」とか思う私の気持ちは、少なくとも主観的には存在している、と思う。だからこそカレー屋に入る、という行動を起こす。そんなのはただの間違っていた「理論的存在」で幻想だ!って言われてもなぁ…。
ここで、「常識心理学」を、「因果的説明」のための道具立てと考えるのをやめてみたらどうだろうか?というのが「解釈主義」になります。
消去主義は、「命題的態度を、行為の原因として認められてはじめてその実在性が認められるものとして理解している」(p.150)。そのために、脳と命題的態度の一対一対応が見られず、命題的態度の因果的な役割が見えなくなった結果、その実在性も否定せざるを得なくなった。
「しかし、心の本質、特に命題的態度の本質は因果性にあるのだろうか。そして、命題的態度の実在性は因果性に基づいて理解されなければならないものなのだろうか。われわれには、命題的態度の本質や実在性を別様に理解する選択肢は残されていないのだろうか」(p.151)。
解釈主義は、命題的態度の本質を、因果性にではなく合理性に求める。「解釈主義によれば、命題的態度にとって本質的なのは、解釈において認められるような命題的態度や行為の間の合理的関係が成立すること」(p.151)であるという。そしてその際に、「命題的態度や行為の間に因果関係が成立する必要はない」(p.151)と考える点が、物的一元論である心脳同一説や機能主義と異なる点である。
例えば、ある人がデパートに、ラッピングされたお菓子を買いに行ったとする。その行為は、「友人にプレゼンをしたい、という欲求のために、かつデパートにはプレゼントとしてのお菓子が売っているという信念を持っていたためにデパートに行った」と「解釈」できる。つまり、ここにおいては、ある人の行為を説明の中で、他の信念やほかの行為と「合理的」な関係にあるものとして、ある欲求や信念は「解釈」されているわけです。
例えば、「その人はそのお菓子を自分で食べたいという欲求を持つのだろう」という「解釈」は、「ラッピングされたお菓子を買った」という事実と「理に合わない」だろう。「それがプレゼントとして買われた」という解釈によってこそ、「理にかなったもの」になる、というわけです。
で、しかしそうなると、解釈主義は「命題的態度」ひいては「心理的なもの」を、どういったものだと考えるのでしょうか?物的一元論のように、「物質的なもの」だと考えるのでしょうか?それとも非物質的な、「心理的なもの」の領域を立てる(つまり「二元論」の立場)のでしょうか?
金杉さんによれば、「解釈主義は物的一元論に対して一定の距離を置いていると言える」(p.153-154)ものの、「二元論に近い立場であることになるわけではない」(p.154)ような立場で、詳しく論じるのは入門書の範囲を超える、ということで「参考文献参照」としています。なのでここら辺は今後の更なる宿題ですね。

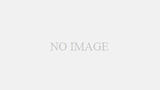
コメント