今回取り上げるのは、志向性とクオリアの関係、という問題です。
知覚と信念を比べてみると、例えば視覚においては、常にクオリア=現象的意識が伴うように思えるのに対して、信念においては、無意識的でクオリア=現象的意識を伴わないようなものもあるのではないか。例えば「地球は丸い」という信念は、普段意識にも上らないが、問題になったときにはすぐに意識に上る。その意味では、常にその信念は持っていた、と言える。しかしそれは「自覚的ではない」という意味でも「意識的ではない」し、例えば地球を宇宙から見ている映像のような視覚像が、必ず伴うわけでもない、つまりクオリアが常に伴うわけでもない、という意味でも、「意識的ではない」と言えるでしょう。
で、ということは、「信念」は志向性を持つ心の状態の一つであるから、志向性を持つ心の状態は、必然的に、クオリアを伴うわけではない、とまず言える。
問題になるのは、逆の形だ。つまり、クオリアを伴う心の状態は、常に志向性を持つのか?という問いです。例えば「もやもやとした感情」や「痛みの感覚」のようなものは、何かを表象しているのでしょうか?
この問いに答えようとするときにポイントとなるのは、クオリアを、先の投稿で区別した、「内在的特徴」「志向的特徴」どちらと考えるのか、という論点です。
記号そのものの特徴が「内在的特徴」で、その記号があらわしている対象に備わる特徴が「志向的特徴」でした。「地球は青い」という文の内在的特徴は、「五文字でできている」とか、「PCのモニターに表示された黒い文字」といったもので、志向的特徴は、地球という対象と、青いという性質、といったことですね。
さて、クオリアとは心の状態の「内在的特徴」なのでしょうか?それとも心の状態が表象する対象の持つ「志向的特徴」なのでしょうか?クオリアを内在的特徴だと考えるのであれば、例えば「痛み」の感覚は、クオリア=現象的意識としての質は持つが、何かを表象はしていない、と考えることができる。
これに対し、クオリアを心の志向的特徴だと考える立場がある。この立場は、クオリアにとって志向性は本質的であると考える。この立場は、「クオリアの志向説」あるいは「クオリアの表象主義」と呼ばれる。(p.111)
で、金杉さんによれば、物的一元論者の多くは、クオリアの志向説を支持するという。クオリアの志向説をとった方が、クオリアを物的一元論の中でうまく位置付けることができるらしい。「らしい」とか書いてしまったのは、正直ここら辺がかなりわかりにくかったのです(笑)。まあ、いずれにしても、ここら辺はまだまだ問題含みで、絶賛論争中、ということらしいです。金杉さんも、参考文献を参照、と書いています。つまり「入門書」の範疇を超える、ということかもしれません。
さて次に論じられているのは、「志向性の説明」です。つまり、「心の状態は、いかにして何かを表象するのか」という問いに答えることです。それは物的一元論の枠組みの中で説明できるのでしょうか?
まず一つ目の説明方式。「因果的説明」。
いわゆる自然物や自然現象においても、「何かを表象している」と言えるのではないか、というものがある。例えば、煙を見れば、その元には火が存在している、と予想するでしょうし、木の年輪は、樹齢を表す、というでしょう。
煙は火を表象するという場合、火は煙の「原因」です。そして、「その因果関係は偶然的なものでなく、それらの間には安定した相関関係があるという点である。たとえば、たまたま火を原因として煙が生じたわけではなく、火がつけばたいていは結果として煙が出ると言える。ここからは、それらの自然的表象の説明として、次のような「因果的説明」が浮かび上がってくる。
因果的説明:XがYを表象するのは、YがXの原因であり、両者の間に安定した相関関係が成立するときかつその時に限る。」(p.114)
これを、心の状態の志向性の説明にも当てはめようとするのが、「因果的説明」である。そして、この説明方式は、物的一元論と相性が良い。心の状態Xとその原因Yの関係を、そのままある脳状態とYとの関係にスライドさせて理解できるからです。
しかしながら、この「因果的説明」には、「誤表象問題」という問題が存在する。例えば、暗がりに蛇を見てびっくりしたのだが、よく見たらひもであった、というような「見間違い」つまり「誤表象」は別に特別なことではない、日常的にありうる事態だ。しかしこの事態を、因果的説明はうまく処理できない。というのも、似たような状況であれば、それは高確率で発生する。つまり「安定した相関関係」を持っている。であるならば、この場合、「蛇の知覚」は常に「ひも」を表象しているのだろうか?それでは、実際に「蛇」を見間違いではなく知覚している「正しい」知覚と区別がつかない。
この、「正しい」「間違っている」という点、つまり「規範的性格」(ひもを表象す「べき」場合がある)をうまく掬い取る説明方式が必要なのだ。
さて、そこで次に考えられるのが、「目的論的説明」である。因果的説明が、心の状態の「原因」に着目するのに対して、結果、すなわち行為に着目する。
例えば、目の前に水があって、のどが渇いていてその水を飲む、という場合。「ある信念が、目の前に水があるという表象内容を持つのは、実際に目の前に水があるときには、その信念が、水を飲みたいという欲求とともに、その欲求を満たすような行為、すなわち水を飲むという行為を引き起こすからである。」(p.118-119)
このように「欲求」に言及することによって、目的論的説明は、「規範的性格」をうまく掬い取ることができるのであるが、次にはこの「欲求の表象内容」の説明が求められる。そしてここで、「進化論的目的」が持ち出される。
「欲求の本質は進化論的な目的に適う行為を引き起こすことにある」(p.121)という。しかし金杉さんによれば、この「進化論的目的」では説明しきれない人間の欲求の問題がある、という。例えば場合によっては持ちうる「自殺したい」という欲求や、「エベレストに登りたい」という欲求は「進化論」的に言えばあまり合理性のない欲求ということにならないだろうか?
というわけで、「因果論的説明」も「目的論的説明」もそれぞれ問題含みである。これらが正しければ、物的一元論にとって有利であるが、まだ決定的な結論を出せない、という。志向性を、それ以上基本的なものでは説明できないものだと考えるのであれば、「物理的なもの」のほかに、「心理的なもの」を認める二元論に有利になるかもしれないが、二元論は二元論で、それはそれで別途その正当化に多くの議論がまだ必要である、という。

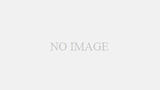
コメント