第三章のテーマは「志向性」です。
出た!「志向性」!
志向性と言えば現象学でも超有名な概念ですよね。でもまあ、いまだにわかるようなわからんような…。あと現象学でも分析系でも使われる概念ですけど、その内実は同じなんだろか…、ってなことが気になりますね。ではでは、お勉強スタートです。
で、まあなんか難しいわけですが。色々疑問も出てきちゃうし。とりあえずはでも、金杉さんの議論というか本の論述を可能な限り再現してみましょう。
まず、「心の」志向性の話をする前に、志向性一般の説明から。
「志向性」とは何か?「あるものが何かを表したり意味したりするはたらきや、何かに向けられている、何かについてのものであるという性質のこと」(p.92)だそうです。「はたらき」や「性質」のことであるからなんというかやはり抽象的な概念ではあるからわかりにくいのでしょうかね?直観的にイメージできるような具体例も出してくれています。
志向性を持つものの代表は、記号や表現といったものです。たとえば、「雨が降っている」という文は、「雨が降っているということ」を表し、富士山の絵は、富士山についてのものである。この時、この文や絵は「志向性を持つ」と言われる。んー…、なんか当たり前すぎることが言われていてかえってぴんと来ない感じですよね(笑)。まーこういう時は細かいとこにはこだわらずにとりあえず最後まで行ってみた方がいいでしょう(笑)。
そんでここでまた言葉を導入します。「表象」です。「志向性を持つものは「表象」と呼ばれ、何かを表すはたらきは「表象する」と表現される。また表象の対象となるものや事柄は「表象内容」あるいは「志向的内容」と呼ばれる」(p.93)。「表象」っていう言葉も哲学をやっている人からすると割とおなじみなんですが、日常では使わない言葉ですよね。「あー、そうやって使うのね」って思うしかない(笑)。
さて、いよいよ「心の」志向性についてです。「信念、欲求、感情、知覚といった心の状態」(p.93)は志向性を持つと言えるのではないでしょうか。たとえば、「雨が降っているという信念は、雨が降っているということを表象し」(p.93)、「目の前にある木の知覚は、目の前になる木を表象している」(p.94)といった具合です。
心のたいていの状態は、志向性を持っているように思われる。「もやもやとした感情」とか「痛み」といった、それが志向性を持つかどうかに関して議論になるものもあるから、心の「全ての」状態が、「必然的に」志向性を持つ、とまで断言するのは控えるにしても、その多くが志向性を持つ、という言い方は許されるでしょう。
さて、では「心の哲学」にとって志向性はどのような含意を持つのでしょうか?
ここで、次の論点が導入されます。先に、志向性を持つものの代表として、「言葉」と「絵」が例示されたわけですが、この二つは、何かを表すという点では共通しているのですが、ある根本的な点で異なります。言葉は「構文論的構造」を持つのに対し、絵はそれを持たない、という点です。では、「心の志向性」は、言葉型の志向性、絵型の志向性、どちらに似ているのでしょうか?あるいは第三の類型なのでしょうか?
「構文論的構造」とはなんぞや?っちゅう話ですが、まずその説明から。
言語には文法というものがありますよね。たとえば語順。「地球は丸い」という文は理解可能ですが、「は地球丸い」という並びにしてしまうと理解不能になります。ということは、語の並びには一定の規則があるわけです。このように語順に限らず、色々なルールがありますよね。
で、他方、先の例での「地球」「は」「丸い」というのは、他の文脈でもそのまま使える要素です。例えば「地球」という語は「地球は青い」という文章にも現れるし、「丸い」という語は「ボールは丸い」という文にも現れます。「このように、構成要素(語)がさまざまな文脈(文)を通して共通に利用されるという特徴を「文脈独立性」と呼ぶ。そして、以上のように、文脈独立性のある構成要素(語)が構成規則(文法)に従って組み合わされている構造のことを「構文論的構造」と呼ぶ」(p.98)。
それに対し、「絵」は「構文論的構造」を持たない。ん?例えば二枚のそれぞれの絵で、赤いリンゴと青いリンゴがそれぞれ描かれていた場合、その「リンゴ」は言語における「語」のような「文脈独立性のある構成要素」ではないの?と思われるかもしれませんね。しかし、それは違う、と金杉さんは言います。
このことを理解するために、またまた新しい言葉が導入されます(笑)。「またかよ!」って思われるでしょうが、今回は特にお勉強色が強い。哲学的な議論そのものの前に、色々な言葉のお勉強が必要なのです。
「表象によって表象されている特徴と、表象自体に備わる特徴」の違いに注目する必要があります。「表象によって表象されている特徴は、「志向的特徴」と呼ばれる。それに対して、表象自体に備わる特徴は「内在的特徴」と呼ばれる。たとえば、「青い」という語の内在的特徴としては、二文字でできているという性質や、(それが黒いインクで書かれている場合には)黒いという性質などが挙げられる。それに対して、その志向的特徴としては、青いという性質が挙げられる。同様に、「地球は青い」という文の内在的特徴としては、「地球」や「青い」といった語を含むという性質や、主語述語構造を持つという性質、五文字から成るという性質などが挙げられる。それに対して、その志向的特徴としては、地球という対象、青いという性質が挙げられる」(p.101)。
さて、表象の「志向的特徴」と「内在的特徴」の区別が理解できたところで、先の論点に戻りましょう。言葉の持つ「構文論的構造」とは何か?そしてそれは本当に言葉だけに特有なのか?絵画だってそれを持っているのではないか?っちゅう問題でしたね。
「志向的特徴」と「内在的特徴」の区別でもって、より正確に「構文論的構造」について説明できるようになります。実は、構文論的構造が持つ文脈独立性のある要素、とは表象の「志向的な特徴」ではなく「内在的特徴」の方に関わるものなのでした。
「地球は丸い」という文と「ボールは丸い」という文において、表象されたもの、においてまず共通点があります。つまり地球もボールも実際の形として「丸い」。そして、「志向的特徴」において共通するものを持つだけでなく、記号としての「丸い」という語を共通にその表現において使っている、という意味でも、つまり「内在的特徴」においても、共通点を持つ。
それに対して、例えば二枚の、リンゴを描いた絵画を考えた時、そこに共通しているのは、「志向的特徴」として同じ「リンゴ」というものを持つ、ということであって、描かれたリンゴの表現そのものは、例えば言語記号における「丸い」という語の持つ汎用性や同一性に比べれば、千差万別だ。むしろ、絵画においては、絵画表現においては、その個別の差異こそが大事だともいえるだろう。赤いリンゴの絵と、青いリンゴの絵は、その「内在的特徴」としては、別に似てもいない。しかし、「志向的特徴」としては、「リンゴという果物」を志向している、という意味では共通点を持つ。
言語の持つ特性は、このように、ある種の抽象性を持った、つまり「地球」にも「ボール」にも当てはまる、(大きさは全く違うのに!)同じ「丸い」という、文脈からは独立している要素を組み合わせて、無限に新しい文を作れるところにある。文脈が変わっても、つまり「地球が丸い」という文においても、「ボールは丸い」という文においても、それぞれにおいて出てくる「丸い」という語を別の単語だとは思わずに、形状に関する形容詞だと、私たちは瞬時に理解する。
さて、では改めて、「心の志向性」は言語のそれと絵のそれ、どちらに近いのだろうか?言い換えると、心の志向性は、「構文論的構造」を持つのだろうか?
「この問いに対して多くの論者は、信念や欲求のように、表象内容を「~ということ」と表現できるタイプの心の状態に着目し、少なくともそれらの心の状態は言語的な表象である、あるいは、言語的表象を一部に含むものだと考える。「~ということ」と表現されるそれらの表象内容はしばしば「命題」と呼ばれる」(p.103)。
命題!出た!「命題」!
これまた哲学とか論理学ではよくつかわれる言葉だから、よく聞くんだけど…。いまだにいまひとつピンと来ないというか…。
金杉さんはこの辺も手際よく説明してくれてます。
雨が降っている、という信念の表象内容、あるいは志向的内容は、「雨が降っている」という「事態」ではないのか?現実に成り立っている、雨が降っていることとは別に、わざわざ「命題」なんて言い方をするのはなぜか?
ということの説明で、良く出されるのが、「明けの明星」「宵の明星」を使っての説明です。で、まずこれらがわからなくないですか(笑)?「おなじみの」明けの明星、宵の明星、って言われても、って。これまた、哲学書を読んでいると、恐らくフレーゲ(という哲学者がいるんですよ)周りの記述でよく見かけます。今ネットで確認したのですが(笑)、フレーゲが「意義と意味について」っていう論文で使っているようですね。
私も、フレーゲの原典に当たってませんが、むかーし読んだ飯田隆さんの『言語哲学大全』とかで見かけた…、気がします(笑)。
で、ですね。要はどっちも「金星」のことなんですよ。明け方と夕方に、太陽との位置関係で地球からも観測される、と。しかし過去の天文学的な知識が今に比べて少なかった人々は、それらを別々の星だと思っていた、と。で、そうなると、以下のようなことになる。「明けの明星は太陽の周りを回っているという信念と、宵の明星は太陽の周りを回っているという信念を考えてみよう。これらの信念の表象内容は、それぞれ、明けの明星が太陽の周りを回っていることと、宵の明星が太陽の周りを回っていることであるが、それらは、世界に成立している事柄そのものとしては、金星が太陽の周りを回っているという同一の事態である。しかし、これらの信念は、一方を信じているが他方は信じていないということが可能であるようなものであり(たとえば、明けの明星と宵の明星が同じ星だと知らない場合など)、それらの表象内容、つまり何を信じているかは別である。それゆえ、それらの表象内容を世界に成立している事柄そのものと考えることはできない。そこで考えられるのが、世界に成立している事柄そのものではないが、それに類したものとしての「命題」なのである」(p.105-106)。
で、しかしまあ、「それに類するもの」って何ぞや、って話なんですが、これに関してはもう別の本を読んでくれ、ってことらしいです(笑)。まあ、「命題」という概念がわかりにくいのもそりゃしょうがない、ということですね。それ自身が議論が必要な概念である、ということですね。まあとりあえずここで確認しなければならないのは、それは「世界で成立していると思われる「事態」」とは別の何物かである、と。
で、信念とか欲求のような、その表象内容を「~ということ」と表現できるような心の状態(それらを「命題的態度」と呼ぶ)は、恐らく言語に類するものであり、「構文論的構造」を持つだろう。
これが心の哲学に対して持つ含意は、心脳同一説や機能主義が正しい場合は、脳状態も構文論的構造を持っていなければならない、という結論が導かれる、ということです。金杉本では、次の章でこの論点が取り上げられていますので、その章を取り上げる際に、またこの論点に触れます。
ふー…、この章はお勉強感が強く、すでに長くなってきましたね。まだ論点が残っているのですが、第三章「心の志向性」に関しては、二回に分けますね。

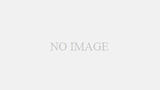
コメント