第二章のタイトルは「心と意識」。「意識」というテーマで考えると、物的一元論には分が悪く、二元論への誘惑を感じる、というのがここでの結論になるようです。
さて、まずは「意識」という言葉の解説から。
日本語で「意識」といったとき、(少なくとも)二つの区別した方がいい意味がある。
一つは、いわゆる自己意識、自覚、というやつです。金杉さんはそちらの方を「反省的意識」と呼んでいます。
「まず、「反省的な意識」とでも呼べるような意識がある。たとえば、私が買い物をしたいと思って店に入ったところ、たまたま、買い物を済ませた友人と会い、おしゃべりをしながら店を出てきてしまったとする。そしてそこで、そういえば自分は買い物をしたかったんだと思い直して、店へと戻るとしよう。このとき、買い物をしたいという私の欲求は非意識的な心の状態から意識的な心の状態になったと言うことができるだろう。このような意味での「意識」が反省的な意識である。「反省」という語には、日常的に、反省の対象に否定的な評価を与えるイメージがあるかもしれない(たとえば、「反省会」という言葉にはそういうイメージが伴うことが多いように思われる)。しかし、ここでの「反省」は、以上のように、当の心の状態そのものについて考えるという意味を持つにすぎない。」(p.60)
しかしながら、今ここでの議論において重要なのは、もう一つの意味です。それは、「現象的な意識」あるいは「クオリア」と呼ばれるものです。
「私が音楽鑑賞をしているとしよう。このとき、私は音楽に夢中になっていて、それを知覚しているという自分の心の状態そのものについては改めて考えていないとする。つまり、この私の知覚は「反省的な意識」という意味では意識的な心の状態になっていないとする。しかし、この私の知覚は、別の意味では「意識的」と言えるように思われる。それは、この知覚体験において、音色や音の強弱など音楽のさまざまな質的な特徴が私の意識に現れてきている、という意味での「意識」である。(改行)さまざまな質的特徴が意識に現れるということは、聴覚だけでなく、その他の知覚や感覚においても生じる。たとえば、さまざまなものごとを見たり、写真や絵画を鑑賞したりするときには、さまざまな色彩や形が意識に現れてくる。あるいは、ざらざらしたものを触るときには、ざらざらした感覚が意識に現れてくる。チョコレートを食べるときには、チョコレート独特の甘みが意識に現れてくるし、カレーの匂いをかぐときには、カレー独特の香りが意識に現れてくる。また、鋭い痛みを感じるとき、鈍い痛みとは異なる独特の痛みの質が意識に現れてくる。このように、われわれが何かを知覚したり感覚したりするとき、それらの知覚や感覚に特有の質的特徴がわれわれの意識に現れてくる。意識に現れるこれらの質的特徴は、しばしば「クオリア」と呼ばれる。」(p.60-61)
さて、この「クオリア」こそが、物的一元論にとって問題となる。「クオリア問題」とは何か?問題は二つ紹介されています。「想定可能性論法」と「知識論法」です。まずは、「想定可能性論法」から見ていきましょう。クオリアの逆転、と呼ばれる思考実験です。
ここに双子の太郎と次郎という二人の人間がいるとします。二人が同じものを見て、二人とも全く同じ物理的な刺激を受けたとする。つまり、二人は全く同じ「物理的な条件」なのです。物的一元論の想定では、二人ともが全く同じ心理状態にならねばならない。つまり同じクオリアがあらわれていなければならない。いや、普通にそうなるでしょ、と思われるかもしれない。しかし、ここで哲学的思考実験をしてみてほしいのです。
例えば、トマトを見れば、二人とも「このトマトは赤い」と言い、夏の生い茂る木の葉っぱを見て、二人とも「葉っぱは緑色をしている」という。さて、その上で、実は次郎は太郎に対して、色のクオリアが逆転していたとしても、表面上何も問題がないのではないか、というのが、「クオリア」の逆転、です。そんなおかしなことがあるか!と思われるかもしれませんが、ここはちょっと冷静に考えてみましょう。哲学的な思考実験です。
ここにおいて次郎の心に現れる色のクオリアは、太郎が「赤」と名指す時に、太郎の心に現れているクオリアと、太郎が「緑」と名指す時に太郎の心に現れているクオリアときれいに逆転している。つまり、太郎がトマトだけでなく、血を見た時にそれを名指す時も、ピーマンを見た時にそれを名指す時も、前者が「赤」で後者を「緑」と名指すのです。つまり、実は次郎と太郎は別のクオリアを、同じ物理的な刺激に対して持つのだけれど、しかしそれに二人とも一生気が付かないのです。
と、ここで気づかれたかもしれませんが、自分もこの「次郎」と同じなのでは?と疑われた方がいるかもしれません。そうです。原理的に言って、他人のクオリアを直接感じることはできません。ということは、そもそも自分のクオリアと、他人に現れている(とされる)それをどうやって比較したらいいのでしょうか?常に、この逆転の想定は可能なのではないでしょうか?
クオリア、というか他人の心の存在は、言葉とか行動で想像したり、いや「想像」という言葉は正確ではないかもしれませんが、なんというか、その存在を確信しているし、それを前提にコミュニケーションを取ったりしているでしょう。
「そこにおいてある赤いものを取って」と次郎が太郎に呼び掛け、太郎が実際に赤いトマトを取って次郎に渡せば、そういうコミュニケーションが続いていけば、次郎は太郎にもちゃんと心が存在する、と信じるのに十分な根拠となるでしょう。
しかしながらついぞ、死ぬまで恐らく次郎は、自分のクオリアと太郎のそれが同じであると確かめることはできないでしょう。である以上、「クオリアの逆転」の想定は常に可能ではないでしょうか。あるいは、自分以外はみな、実は、この、私が持っているようなクオリアを、まったく持っていないのではないか?というクオリアの「欠如」の想定(ゾンビ、あるいはロボット?の想定)すら可能ではないでしょうか?
そして、これが可能であるのならば、物理的には全く同じ、と想定されていた以上、太郎と次郎において別のクオリアが、つまり心理状態が成立しているのではないか?そしてそうなれば、「心とはつまるところ物質である脳であり、脳の状態が同じであれば、それによって生じる心の状態も同じである」という考えも危うくなります。
というのが一つ目の「想定可能性論法」です。そして次に紹介するのが「知識論法」と呼ばれる議論です。
まず、改めて物的一元論の前提を確認しましょう。「まず、心の状態に関する事実を「心的事実」と呼び、物理的状態に関する事実を「物理的事実」と呼ぶことにする。物的一元論によれば、心の状態とは主体の何らかの物理的状態である。したがって、物的一元論によれば、すべての心的事実は何らかの物理的事実にほかならない。」(p.75)
さて、その上で、また哲学的な思考実験をしてみましょう。ある天才的な科学者がいた。その人は生まれてすぐに、色覚を失わせる手術をうけた。なので、例えば「空の青さ」を、見たことがない。しかしながらその人は天才科学者であった。あらゆる科学的な知識に通じている。すべての「物理的な事実」を知っている。なので、たとえば「もし自分が青い空を見たとしたら(実際には見たことないが)、自分がどのような物理状態になるかといったことに関する事実も完全に知っている」(p.75)。
そんな科学者が、再手術を行い、色覚を回復させて、青い空を見たとする。そのときこの人は、「青い空とはこんな色だったのか!初めて知った!」と述べるのではないだろうか?つまり端的に言って、「物理的な事実」には尽くされない「心理的な事実」といったものは存在する!よって、物的一元論は誤っている。
以上が、物的一元論に対する批判としてのクオリア問題です。それに対しては物的一元論からの再反論も可能です。まず、「想定可能性論法」に対する反論。
「想定可能性論法」は以下のようにまとめられる。
「前提1:物的一元論が正しいならば、同一タイプの物理的状態にある二人の主体が異なるタイプの心の状態にあるということは不可能である。
前提2:クオリアの逆転や欠如の状態、すなわち、同一タイプの物理的状態にある二人の主体が異なるタイプの心の状態にあるということは想定可能である。
結論1(前提2から):同一タイプの物理的状態にある二人の主体が異なるタイプの心の状態にあるということは実際にも可能である。
結論2(前提1と結論2から):物的一元論は誤りである。」(p.77)
さて、これに対して物的一元論はどうこたえるのか?前提2から結論1を導出している点が間違いである、とします。あることの「想定可能性」から、そのことが「実際に可能であること」は一般に出てこない、とするのです。これを説明するために、物的一元論者は、「水とH₂O」の事例を出します。
「水が(1気圧の下で)80度で沸騰するということが想定可能かどうか、またそれが実際に可能かどうかを考えてみよう。水の本質、すなわち、水とはH₂Oであり、H₂Oの分子構造からして水は100度で沸騰するということを知っている人にとっては、それは想定不可能である。それに対して、水の本質に関するこの化学的知識を持たない人(子どもや昔の人など)にとっては、それは容易に想定可能だろう。しかし、誰にとってであれ、水の本質からして、水が80度で沸騰するということは実際には不可能である。したがって、後者の人々(子どもや昔の人など)にとっては、それは想定可能であるが実際には可能でないということになる。それゆえ、一般に、あることが想定可能だからと言って、それが実際にも可能であるとは言えないのである。」(p.78)
それゆえ、昔の人が水の本質をよく理解していなかったように、「現象的意識」や「クオリア」の本質について私たちがまだ理解してないだけかもしれない、というわけだ。
「知識論法」に対する反論はこうです。まず、また知識論法の推論をまとめましょう。
前提1:物的一元論が正しいならば、すべての心的事実は何らかの物理的事実である。
前提2:科学者は、すべての物理的事実を知っていたが、青い空を見て初めて、青のクオリアが意識に現れるとはどのようなことかを知った。
結論1(前提2から):物理的事実でない心的事実がある。
結論2(前提1と結論2から):物的一元論は誤りである。
(p.80-81を基に作成)
そしてここでも、前提2から結論1を導出していることが誤りだという。「すでに知っていた事実を異なる仕方で認識するに至る場合」(p.81)が一般にあると言い、そしてその場合は、何か新しい別の事実を知ったわけではない、という。例えばこんな例。
ある棒の長さを、メートル尺を使って測り、それが1メートルであるという事実を知ったとする。その上さらに、同じ棒を、ヤード尺を使ってそれが1.1メートルだということを知ったからと言って、「新しい別の事実」を知ったことにはならないのではないか。これと同様、先の科学者は、青い空を見た時、「新たな事実を知ったのではなく、すでに知っていたある物理的事実をこれまでとは異なる仕方で認識するに至っただけ」(p.81-82)と考えることもできる。
さて、このように、批判には応答することができる。しかしここで行われていることは、「想定可能性論法も知識論法も物的一元論の誤りを示そうとする論証としては不十分である」(p.84)ことを示しただけである。別途、物的一元論が本当に正しいかどうかは、さらにそれ自体の証明が必要である。
しかしながら、このクオリア問題に即して考える限り、そこには「説明のギャップ」というものが存在すると金杉さんはいう。
例えば先の水の事例とのアナロジーは本当に成立するのだろうか?
「水とH₂Oの同一性の説明は、(実際にそれが発見された道筋とは異なるかもしれないが)次のように再構成できる。まず、水が持っているさまざまな性質が特定される。そして、それらの性質はすべて何らかの因果的役割に分析される。たとえば、「(1気圧では)100度で沸騰する」という性質は、「100度まで加熱する」という原因によって「気化を始める」という結果を引き起こす、という因果的役割に分析される。そして、今度は、このような因果的役割を果たす性質を持つミクロ的な実体が探し求められる。そして、H₂Oという分子構造を持つミクロ的実体の一群がそのような性質を持っているということが確認される。それゆえ、水とはH₂Oにほかならないと納得のいく形で結論できるのである。」(p.86)
このように、因果的役割による分析は、物理的なもの同士であるからこそ、可能なのではないか?「水」と「H₂O」はともに物理的な性質を持つ。それに対し、脳とクオリアは似たような関係にあるのだろうか?まさに、そこに何か直観的に違和感を感じるからこその、そこに「説明のギャップ」があるからこそのクオリア「問題」なのではあるまいか?単に科学的な進歩の問題で、いまだ同一性が明らかになっていないのではなく、ある本質的な理由によって、それらを同一なものとしてとらえることができないのではないか?
さて、このように、現象的意識、クオリアとしての「意識」に注目することによって、物的一元論にも不十分な点があること、二元論にも一定の誘因があること、がわかる。

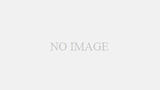
コメント