「論文を書く!」とぶち上げたものの、さっそく停滞しております(笑)。
うー…ん。どうしたもんか、と思いまして、また計画を練り直すか、と。
で、改めて入門書を読んで勉強することにしました。
メルロ=ポンティや現象学の枠組みで心身問題に取り組もうと思っているのですが、この本は『現代現象学』の文献案内でも紹介されていたし、何よりもずっと積ん読状態でしたので、主に分析系での議論における「心の哲学」の紹介ですが、私にとっても勉強になるだろう、ってことで『心の哲学入門』(金杉武司著 勁草書房)を読みました。
さて、「勉強ノート」として、本の内容や読んで考えたことについて書いてみようと思います。
「心の哲学」のテーマは、もちろん「心とは何か」という問いだ。しかしながら、こういった抽象度の高い問いに対し、腕を組んで「うーん、うーん」と考えていれば勝手に答えがひらめく、ということはあまりない。そこで、一つ補助線を引く。例えば、「心とは何か?」と直接問わずに、「ロボットは心を持ちうるか?」と問うてみる。
恐らく考えられうる答えのパターンとしては以下のようになるだろう。
「(1)持ちえない(以下、その根拠)
①心は生物しかもちえないものであるのに対して、ロボットは人間が作った機械(人工物)だから。
②心を持っている人間には、自ら考えたり行為したりしようとする自発性があるが、プログラムに従っているだけのロボットにはそのような自発性がないから。
③心の状態の一つである「感情」は、非常に多様で複雑なものであるのに対して、二進法(0か1か)のプログラムに従っているだけのロボットはそのような多様性や複雑性を示しえないから。
④心は非物質的なもの(魂のようなもの?)であるのに対して、ロボットは物質の塊に過ぎないから。
(2)持ちうる(以下、その根拠)
①人間は物質の塊であり、それゆえ、心のはたらきも物質のはたらきに他ならない。そして、物質の塊であるという点ではロボットも人間も同じだから。
②心のはたらきとは脳のはたらきに他ならない。この脳のはたらきを解明してロボットの脳にそのはたらきを組み込むことはいずれ可能になるだろうから。
③心の多様性や複雑性とは、結局のところ、「ペットが死ぬと悲しむ」とか「宝くじが当たると喜ぶ」といったパターンを複雑化したものにほかならない。それらの複雑なパターンを実現するプログラムを見出して、それをロボットの脳に組み込むことはいずれ可能になるだろうから(現在は単純なプログラムしか組み込めないが)。
④ロボットのプログラムは人間に決められた単純なものからスタートするしかないかもしれない。しかし、ロボットもさまざまな経験や学習をすることができ、これらの経験や学習を通して自発性や複雑性が生み出されると考えられるから。
(3)わからない(以下、その根拠)
①「心」とは何かをわれわれはよくわかっていないから。
②「心」を定義してくれなければ、かんがえようがないから。」(p.3-4)
(3)の選択肢がそもそもありだと思われてなかったりするが、まあよく考えると、「わからない」と答えるしかない。しかし、この問いは、正解を出すのが目的というよりも、これを一つのきっかけとして、「心とは何か」という問いを進めていくためのものだ。
これらの答えの中に、問いを推し進めていくヒントがある。
確かに、私たちは「心」とは何か?についてはっきりとは答えられない。とはいえ、普段「心」という言葉を使ってコミュニケーションをとっているし、心について全く何も知らない、ということではない。(1)の③で出てきた「感情」は、心に含まれているものだろう、といったことぐらいは言ってもいいのではないか。「感情」以外にも、何かに関する「思考(哲学では特に「信念」といったりする)」とか、「欲求」や「知覚・感覚」といったものが、それこそ正確には心の「働き」なのか「心そのもの」といった方がいいのか、といった問いには答えられないまでも、心とは関係のあるものだ、ということまでは断言してもいいだろう。
このように、心について私たちはすでにある種の知識というか、常識みたいなものを形成している。それらのことを「常識心理学」とか、「素朴心理学」「民間心理学」と呼ぶ。そして、哲学的な反省は、徹底的であることが要求されるから、時には常識も疑うのだが、何でもかんでも疑えばいい、ということでもない。そのようにすべてを疑うのであれば、そもそも「心とは何か?」という問いを立てることすらもできないだろう。であるから、このような常識を土台とすること自体は構わない。というか、ある種の土台を作らなければ、こういった問いは問い進めることすらできない。
さて、ではどのように問いを進めていくか。先の答えの中で、「常識」というよりも、実はそれ自体が改めて問われる必要のある、心の哲学における一つの結論、一つの理論的立場であるものが含まれている。(1)の④における、「心は非物質的なものである」という考え方や、(2)の②の、「心のはたらきは脳のはたらきに他ならない」といった考えだ。
どちらも説得的であるが、よく考えると、それが正しいのかはわからない。そしてさらに言えば、心が「非物質的」なものであるという考え方と、結局のところ「脳」という物質に還元されるという考えは矛盾しそうだ。
しかし矛盾しているからこそ、ここら辺にポイントがあるのではないか。
「心の哲学」や「心身問題」に対する回答、理論には様々なものがありうるが、この本では、二つの考えに回答の候補を絞っている。それは「二元論」と「物的一元論」だ。それぞれ以下のような立場だと言える。「二元論のテーゼ:心は非物理的な存在であり、世界はこの非物理的な存在と物理的な存在の二種類の存在によって構成されている」(p.12)。「物的一元論のテーゼ:世界は物理的な存在のみによって構成されている」(p.13)。
現在の常識では、心が結局は脳にほかならない、ってみんな思ってるんじゃない?二元論って「魂」みたいなもんを認める「非科学的」なものなんじゃないの?と思われるかもしれない。しかし仮に心が脳と密接な関りを持っていることを認めるにしても、その時の「密接な関り」というのは厳密にいうとどういう関係なのだろう?そして、心は脳が原因で発生するが脳とは存在論上は区別される別のものだ、と考えるのと、心と脳は「同一のもの」だ、と考えるのとでは、違う考えだ。そして前者のように考えられるのであれば、それはもはや「物的一元論」ではなく「二元論」であり、かつこの二元論において「魂」といった非科学的な(と考えられるかもしれない)ものを認める必要はない。
「二元論」と「物的一元論」とはそれぞれ、その立場をとりたくなる理由がある。まず二元論。人間以外の動物、例えば犬や猫は白黒の世界を知覚している、と言われる。あるいはアメーバにとっての「世界」というものはどういうものかを想像したり、ある種の超音波的なもので知覚していると言われるコウモリにとっての意識といったものを想像してみると、客観的な世界は一つだが、それぞれの主体の「中で」別々の意識世界が構成されているのではないか、と考えたくなるだろう。そうすると、客観的な物理的な世界の他に、主観的な「心」の世界を認めた方がいいのではないか?
しかし他方、科学的な世界観の発展の中で、例えばかつては生命現象を説明するために持ち出された「生気」といった非物理的な概念が使われなくなり、物理学的な説明がなされるようになったように、「心」もたとえば脳の物理学的な解明により、不要な概念であったことが明らかになるかもしれない。そうなると、「非物理的な」心というのは余計な概念で、「物理的なもの」だけで世界を説明する物的一元論の方が正しい気もしてくる。
さて、ということで、この本では主に二つの立場「二元論」と「物的一元論」が検討されている。
心が持っていると思われる特徴を検討することによって、どちらの立場が説得的か、論じようとしている。その特徴は五つ。
1.心の因果性
2.心と意識
3.心の志向性
4.心の合理性
5.心の認識
さて、次回からはこれらを具体的に一つ一つ見ていこう。

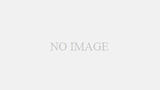
コメント