今回取り上げるのは「価値」という概念です。
今まで取り上げてきたエクササイズは、「脱フュージョン」にしろ「拡張」にしろ、なんというか、消極的なものだという印象を持たれてしまったかもしれませんね。サッカーやバスケのようなスポーツに言う「ディフェンス」というか。つまりあくまでストレスや感情的悪循環というマイナスなものをどう減らすか、そういったものをどう防ぐか、という話ですね。
もちろん、人生においてストレスやマイナスな出来事とどう付き合っていくか、というのも大事なテーマですし、それらをうまく処理できるようになることは、「人生が変わる」と言ってもいいくらいの出来事ではあるでしょう。
しかしながら欲を言えば、もっと積極的に、「人生を変えたい」、つまり仕事が嫌なら転職したい、とか、ただストレスを減らすだけでなくより積極的に、人生を楽しいもの充実したものにしたい、とも思わないでしょうか?
いわばこの積極的側面、「オフェンス」的側面を担当しているのが「価値」なのです。
さて、ではACTにおける「価値」という概念はどういうものか?
「心の中のもっとも深い欲望。何になりたいか、どんなものを支持したいか、世界とどのようにかかわりたいかなど」(p.202)のこと。
ハリスは、「価値」と「目的」を区別することが大事だ、と言います。「価値」というのは、例えば航海における「北極星」のようなものだと言います。
例えば、「西に向かって旅をする」ということを考えてみましょう。「西」とは具体的な場所ではなくて特定の「方向」ですよね。いくら歩いても歩いても、「西そのもの」には一生たどり着きません。
この比喩で言えば、「目的」というのは、具体的な「あの山」や「この川」のことです。「西を目指して旅をする」となったら、まずは差し当たっての目印となる身近な何かを目指すでしょう。例えば今遠くに、しかし目視で見えている「あの山」を。
そして差し当たってのその山についたら、まずは最初の「目的」は達成、です。そして目標リストからは「〇〇山」は到達済み、としてチェックして消されます。そして次の西側にある何かランドマーク的なもの、例えば「××川」を目指すでしょう。
このように、私たちの行動を方向付け動機づけてくれるが、それ自体は達成されてなくなることのないような原理のことを「価値」と呼んでいます。
具体例として例えばハリスが挙げているのはこんなものです。
「価値と目的を混同しないことは大切だ。価値は私たちが目指す方向であり、終わりのない進化のプロセスだ。愛に満ちた気遣いのあるパートナーになることは価値のひとつだ。それはあなたの人生における終わることのないプロセスだろう。愛と気遣いを止めた瞬間、もはやその価値に沿っては生きていないことになる。
一方、目標は望んでいる成果であり、達成可能なものである。たとえば結婚することは一つの目標だ。達成されればそれで終了であり、目標リストの中から消去される。結婚してしまえば、愛情深く優しかろうと、冷たくぶっきらぼうであろうと、あなたは既婚者だ」(p.205)
さて、このような意味での「価値」を、どのようにすれば明らかにできるのでしょうか?
ここでもハリスは、いくつかのエクササイズを用意してくれています。それらをご紹介します。しかしながらここで言っておかなければならないのは、私もまだまだ価値に関して確信は持てていない、ということです。「脱フュージョン」や「拡張」「接続」に関しては、それなりにエクササイズを重ねて、実感できる部分があるので、自信を持ってお勧めできました。
しかし「価値」に関してはまだまだ、おぼろげながら見えてきたかな、というくらいです。自信をもって「これで俺の人生変わりました!」みたいに断言できるほど素晴らしい人生を送っているわけでもありませんしね。それでも最近、休日ダラダラ無目的に時間を浪費して仕事前に憂鬱になる、なんてことが少し減ってきた気はしてます。
さて、ではどのようにして自分にとっての「価値」を明確にしていったらいいのでしょうか?質問に答えることによってそれを明らかにしていきます。質問に対する答えは、ただ頭の中で考えるのではなく、紙に書き出してみることをハリスは推奨しています。そうする方が、意識にも残りやすく、明確にしやすいようです。
まず三つの質問。
「自分が八十歳になったつもりで、人生を今日一日の出来事のように振り返ってみよう。そして次の文章を完成させよう。
・私は……を恐れることにあまりに多くの時間を費やしすぎた。
・私は……のようなことにほとんど時間を使わずに来た。
・もし時を戻せるなら、今までやらなかったことで、何をするだろうか。」(p.207-208)
このシンプルな質問で、自分の本当はやりたかったがやれなかったことについて思い出せるでしょう。
日本におけるACT研究の第一人者である武藤崇さんの著書『ACT 不安・ストレスとうまくやるメンタルエクササイズ』(主婦の友社)における以下の質問もいいヒントになるんじゃないでしょうか。「もし十億円手に入ったら」という質問です。十億円が急に手に入ったら、今の仕事を続けるだろうか?貯金して家族と静かに暮らすことを選ぶだろうか?それとも何か事業を始めるだろうか?いずれにせよ、そこには自分の欲望が反映されているのではないでしょうか?
こんな感じで、質問に答えていく中で、少しずつ価値を明らかにしていくことができます。「少しずつ」です。逆に言うと、これらの質問に答えても、一発で「これだ!」って思える決定版の答えには出会えないのでは?と思います。「いや、こんなのが俺の「価値」だろうか?」「俺は俺の本当の気持ちがもうわからない…」とか色々疑念も出てきてしまうからです。私もそうなりました。この質問に答えようとすること自体に不安になってしまうというか。
ハリスも、時間は十分にかけよう、と言っています。そしてそういう疑いの思考自体が、それこそ今まで論じてきた、心がささやく思考、物語、「破滅と憂鬱ショー」の1プログラムなのです。そういったネガティブな思考に釣りあげられたら、そっと針を外し、また作業に戻りましょう。
ハリスによれば、「心の奥深くであなたが望んでいることは何か?」と問うと、人々の答えは大体以下のようになるそうです。幸福になりたい。金持ちになりたい。成功したい。尊敬されたい。立派な仕事に就きたい。結婚して子供が欲しい。というような。
ハリスは別に、こういった答えを否定しているわけではないのですが、しかしそういった答えは、「特に「深く」内省され、考え抜かれた答えではない」(p.209)という。
では、どうすれば「深く」考えることができるのか?
4つのジャンルに分けて、それぞれについて質問に答えて考えていくことが推奨されている。1.人間関係。2.仕事・教育について。3.個人的成長・健康。4.余暇。という4ジャンルです。
これら4つの領域に関して、それぞれ質問が用意されています。一つ一つ見ていきましょう。
まず、人間関係。
・どのような関係を築きたいと思っているか?
・こうした関係の中でどのようにふるまいたいか?
・どんな個性を育てたいか?
・あなたが「理想の自分」であったらとしたら他者にどんな風に接するか?
・これらの人々のうち何人かと一緒に、一生続けたい行動は何か?
(p.211)
これらの質問に答えようとすると私たちは、「どんな友人、どんなパートナーが欲しいかを説明する」(p.212)場合が多いそうなのだが、それは「目標」であって「価値」ではない。ハリスの言う「価値」を明らかにするためには、さらにこう問うてみてほしいそうです。「自分の望むパートナーや友人がいたら、彼らにどう接するだろうか?彼らとの関係に、自分のどんな性質を持ち込みたいだろうか?」(p.212)と。
仕事・教育について。
・職場、あるいは学校に、自分のどのような資質を持ち込みたいか?
・「理想の自分」になったら、同僚や従業員、顧客や依頼人、同級生にどのように接したいか?
・職場や学校でどのような人間関係を築きたいか?
・どのようなスキル、知識、資質を開発したいか?
(p.213)
ここにおいても、人は「価値」ではなく「目標」について語りがちだそうです。つまり「理想の職場」について語ってしまう、と。でもそうではなく、仮にあなたが理想の職場にいたとしたら(逆に言うと、嫌な職場にいたとしても)、あなたの行動はどう変わるか、職場にあなたの資質のどんな点で寄与したいか、について考えてほしい、というのです。
個人的成長と健康に関しては、まあそのままですが、例えば健康を気遣わない人はあまりいないとは思いますが、健康のためにどんな活動をしていきたいのか、どんなライフスタイルで生きたいのか、等が「価値」になるそうです。
余暇について。休日の活動について、どんなことを人生でやりたいか、ということだそうです。
さて、これらの項目について十分に書きだしたら、どの要素について最もよく取り組んでいるのか、逆に一番無視していることは何か、一番重要で今すぐ取り組むべきなのは何か、について考えましょう、ということです。
価値が明確になったら、次に具体的な目標を定めます。そしてそれに従って具体的な行動を起こしましょう、という順番になります。
目標を定めるためにまず、上で確認した「価値」を明確に言語化します。例えばこんな感じ。「家族という分野では、私はオープンで正直、愛に満ち、助力を惜しまないことに価値を置いている」(p.223)。分野は、最初は一つに絞った方がいいとハリスは言っています。初めから複数の分野に同時に変化を起こそうとすると、圧倒されてかえって嫌になり失敗する可能性が高いそうです。しかし逆に、一つのジャンルでうまくいくと、自然と他のジャンルにも変化が波及する(「ドミノ・エフェクト」というそうです)ことが多い。
さて、価値がはっきりしたら、それに沿った具体的な目標を、4段階に分けて考えます。まず最初に、最も簡単にできる、ハードルが低い行動を考えます。先の家族の例なら、「昼休みに家族に電話して愛していると伝える」といったような。なるべく細かく、詳しく決める方が実行率は高くなるそうです。例えば「もっとエクササイズする」というよりは、「週に二回、三十分泳ぐ」とする。
そしてだんだんとスパンを長くして、さらに三段階考えます。つまり、短期、中期、長期、です。短期は数日から数週間。中期は数週間から数か月、くらいの感じです。そして長期は、数年という単位で考え、ここは大胆に考えることが推奨されています。五年後にどうなっていたいか、と。別に失敗しても構わないので、大きく考えるのが良いようです。
そしてさらに、目標を決めたら、「行動計画」を立てる。「あなたの価値がエクササイズをすることで目標は週に三回ジムに行くことだとする。あなたの行動計画はまず、1.ジムに入会する、2.ジムで着るウェアを手に入れる 3.ジムに行く時間を決める 4.スケジュールを見直して行動できるように調整する。あなたが必要なのは、a.ジムに入会するためのお金。b.ジム用品(スニーカー、短パン、Tシャツ、タオル、それらを入れるバッグなど)。次に、これらの作業をいつやるか具体的に決める。たとえば「今晩荷物をバッグに詰める。明日仕事の後ジムに行く。そして最初のエクササイズを始める」などだ」(p.228)。
このように細かく決めるのはやりすぎでは、と思われるかもしれませんね。しかしハリスによれば、実際に行動を起こせば、おおらかさはやがて発揮できる、という。初めの段階では、慣れるまでは多少人為的なぐらいが意識的に行動を変えるためにはいいのかもしれません。慣れてくると、ここまで形式ばった形でなく、自然と、「価値―目標―行動計画」と頭の中に描けるようになるそうです。「そうです」というのはつまり私もその段階ではないので断言はできませんが(笑)。
ここで注意点は、「目標達成」にこだわりすぎないようにすることみたいです。ハリスは、二人の子供の例を出しています。家族で旅行に行っているとする。片方の子供は、目的地に着くまでの車中、「まだ着かないの?」とぐずり不機嫌。それに対しもう一方の子は、車窓から見える風景自体を、旅の一こまとして楽しんでいた。目的地に着けば、二人ともが目標に達して満足するのは同じだが、もし仮に予定が変わって旅行が中止になったとしたら、旅を楽しめたのは後者の子だけだ、というたとえ話です。
そしてこれは私たちの人生も同じだ、というのです。目標を目指して努力することは、確かに私たちの人生を意味のある、充実したものにするのだが、そのことは、目標を達成しないと幸せにはなれない、ということを意味するものではありません。後者の子供のように、目的への道中そのものを、成功へのプロセスの努力そのものを、人生の中の充実した一コマとして味わい楽しめれば、実は目標を立てて行動を始めた瞬間にもう私たちは幸福なのです。

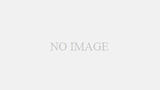
コメント