今回取り上げるテクニックは「拡張」です。
「拡張」とは、嫌な、不快な感情を受容するためのテクニックです。具体的には、意識を集中しながら深呼吸を行う、といったものになります。
私個人としては、この本を読む前からマインドフルネスの本を読んで呼吸を数える瞑想の実践をやっていたので、このエクササイズが一番入りやすかったです。そしてシンプルな方法ですので誰でもやりやすいと思いますし、実践的な効果も感じやすいと思います。なのでACTの数あるエクササイズの中でも特にお勧めしたいものです。
さて、しかし今回もまた、具体的なエクササイズの紹介に入る前に、いくつかの説明が必要です。それ自体もお話としては興味深いものです。「感情」とは何か?というお話です。
「感情」とはそもそも何なのか?
科学者たちの研究において、答えの決定版、完璧な定義、はまだ存在しないそうです。しかしながら、現状でも合意がある程度とれる共通認識はある。
1、感情は「中脳」と呼ばれる脳の中間層で発生する。
2、どんな感情の中心にも、体全体に起こる複合的・連続的な身体的変化がある。
3、この身体的変化は我々に、次の行動の準備をさせる。
(p.100)
「感情」とはもちろん「心」のカテゴリーに含まれる事柄ではあるが、例えば不安な時に、「胸の奥がつかえるような感じ」があったりとか、緊張で手が汗ばんだりするでしょう。それらがつまり「身体的変化」ですね。ホルモン分泌量や神経システムにおける変化のように、それ自体は体感や自覚があまりできない変化も含みます。
そして、そういった身体的な変化は、次にとるべき行動の準備となっています。つまり特定の感情には、特定の行動をとらせる力があるわけです。
しかしこれはあくまで特定の行動をとらせる「傾向」を持っているということであり、それ以外の行動はとれなくなる、ということではないことをハリスは強調します。つまり、誰かに対し強い怒りを感じた時には、その人を怒鳴りつけたくなったり、場合によっては、殴りつけたくなる衝動に駆られる。しかし実際の行動においては、そういった「傾向」に逆らい、あえて抑制的に話す、といったことを私たちはできます。
つまり、「感情が行動を支配する」というのは強力な幻想にすぎない、とハリスは言います。これが、ACTが「行動」を重視する理由です。感情は私たちの自由になりにくいですが、行動はそうではありません。
さて、そしてハリスは、感情を「天気」に例えています。
「天気」というのは、その下位区分としての、個別の出来事である「雨」「雷」「晴れ」等を含む一般的な概念です。つまり雨がやんでいる時間があっても、「天気そのもの」が存在しなくなる瞬間はない。
で、「感情」というのはいわば「天気そのもの」のようなもので、常に存在します。そして例えば個別の特定の天気「雨」や「雷」が、「悲しみ」とか「怒り」とかの特定の個別的感情に該当します。
そして感情は生まれる時、三つの段階を経るそうです。
第一段階:重大な出来事が起こる
第二段階:行動の準備をする
第三段階:心が巻き込まれる
第一段階の「重大な出来事」というのは、外の世界で起こる出来事だけではなく、内面の出来事も含みます。つまりつらい記憶とか、自分を動揺させる内面の思考がきっかけになることもあります。
そしてそれらの出来事に脳が気付くと、判断を行います。「その出来事は良いことか?悪いことか?」「利益になることか?害悪になることか?」
良いことであり、利益になることであれば、対象に近づく必要が出てきます。悪いことや害悪だった場合は、その対象と戦うか逃げるかしなければなりません。いずれにせよ、この第二段階では、「行動の準備」を行います。この段階ではまだ、それとはっきりわかる感情としての「気分」はまだ存在しません。
第三段階になって初めて、行動の準備が整いだすのと同時に、対象の価値に合わせて、フラストレーション、喜び、悲しみ、怒り、等の個別の感情が生まれてきます。
ところで、「闘争・逃走反応」という言葉をお聞きになったことはないでしょうか?第二段階において、脳が出来事を、「害」と判断した際に、発動する反応です。「闘争・逃走反応は、中脳で発生する原始的なサバイバル反射作用だ。この作用は、脅威にさらされた時生き残るために逃走するか、踏みとどまって戦うかという二者択一とともに進化してきた。心拍数は上がり、アドレナリンが分泌され、血液が腕や脚の筋肉に流れ込み、呼吸の回数が増え、より多くの酸素が取り入れられる。これらはすべて、闘争・逃走の準備を整えるためである」(p.105-106)
いわゆる原始時代には、この反応はとてもよく機能した。マンモスが突進してきたときに、我々がとりうる行動は戦うか逃げるかのどちらかだろう。そしてその判断の失敗は即、「死」を意味する。
しかし、その進化の果ての、われわれの生きる現代社会においても、それはよく機能するだろうか?
我々の社会で、「マンモス」や「サーベルタイガー」とは頻繁に遭遇するわけではない。私たちが心配していることは何か?
「こうなると進化は犯罪だ。殺されないことを念頭に置く私たちの心は、ほとんどすべての状況に危険を感じてしまう。不機嫌な伴侶、支配的な上司、駐車違反のチケット、新しい仕事、交通渋滞、銀行の長い列、長期のローン、鏡の中の冴えない自分など。脅威は、不快な思考やイメージといった形で心そのものからももたらされる。これらは何一つ命を脅かすものではない。しかし私たちの脳と体はそう捉えてしまうのだ」(p.106)
私たちは一般に、感情を「ポジティブ」なものか「ネガティブ」なものに分けますね。喜怒哀楽で言えば、喜びや楽しいことは快いものであり、ポジティブな感情で、怒りや悲しみは、不快でネガティブな感情だ、と。
実際、悲しみや不安は感じたくはないですよね。しかしながらそういったものを人生から完全に排除することは難しいでしょう。「だから喜んでそれらを受け入れましょう!」なんて言っても、無理な話です。それこそ絵空事の「物語」というか、理想論というか、それができたらそれに越したことはないけど…、という感じでしょう。
燃え盛る火に手を触れれば、熱さというか、むしろ「痛み」として感じられる感覚を手先に感じ、反射的に手を引っ込めるでしょう。それは生き物として当然の反応です。
精神的な苦しみや痛みはどうか?まあ、身体的な痛みとは一応は区別はされるかもしれませんね。反射的に逃げるというほどではなく、一応それに対する反応を考えて選んだりすることはできますね。例えば、休み明けの月曜日の朝仕事前。仕事に行くことはとても「嫌なこと」だ。「憂鬱」でさえある。しかしながら、私たちは頑張って、重い体を引きずって、出社する。
そこでどう考えるか?「こんな感情なければいいのに」と思う。「転職すればこんな気持ちにはならないのだろうか?」「そもそも俺の人生なんでこんななんだろ?」「なんで大金持ちの家に生まれなかったんだろ?」「若いころから引きこもらずに、何かのジャンルで努力して、経済的な「成功者」になっていればなぁ…」
ってな具合に、色々な思考が頭を駆け巡らないだろうか?
ACTでは、「きれいな不快感」と「汚い不快感」を区別します。人生で避けることのできない、自然な不快感のことを「きれいな」不快感と呼び、その原初的な感情に対する、思考による価値判断や評価、自意識が生み出す第二段階のそれを「汚い」不快感と呼びます。
生きていて不安な出来事に出会うことは避けられない。特に例えば、新しいチャレンジをするときなどに感じるそれは、「避けられない」だけでなく、自分にとって有益なものをもたらしてくれるものでもある。しかしやはりそれは「不快」なものではある。そしてそれから逃げてしまったりする。
そして悪い場合にはさらに、そんな自分を責めてしまったりしないでしょうか?「なぜ俺はこんなに不安がりで情けない男なんだ!」と自分に怒りを感じたり、絶望を感じたり。この場合の最初の不安は、「きれいな」感情です。しかし後の方の「怒り」や「絶望」のことをACTでは「汚い」感情と呼びます。
このように、私たちは「悪循環」に陥るのです。ある不快な感情に対し、ただ感じるのではなく、それを否定しようとしたり、価値判断を加えたり、じたばたとあがいてしまうのです。これがまさに「幸福の罠」です。そしてハリスは、「悪あがきのスイッチ」という言葉を持ち出します。
心の中には、「悪あがきのスイッチ」があると考えてほしい、と。それがオンになっていると、私たちはネガティブな感情に対し、じたばたと悪あがきし、さらなる「汚い」感情を生み出し、感情を増幅し、不幸の沼へとずぶずぶとはまっていくのです。
沼にはまったときにやるべきことは、じたばたと暴れることではなく、じっと横になり、浮かんでいることです。(ハリスは西部劇等で描かれる「流砂」で喩えていますが)
で、じゃあどうすればいいのか、というと、ここで出てくるのが「拡張」というテクニックです。
「拡張」は四つのステップからなる。1、自分の気持ちを観察する。2、息を吹き込む。3、居場所を作ってやる。4、存在を許してやる。
「・ステップ1 観察する
体の中を観察する。数秒かけて、頭からつま先までをスキャンしてほしい。するといくつか不快な感覚があることに気づくだろう。一番不快なものを探してみよう。例えば喉の奥の詰まったような感覚、胃がギュッと締め付けられるような感じ、涙が溢れる感覚など(体全体が心地よくない場合は、一番不快感のある場所を見つけよう)。次にその感覚に注意を向ける。新しい現象を発見した科学者のように、好奇心をもってその部分を観察しよう。それがどこから始まってどこで終わっているか。その感覚の輪郭を描くとしたら、どんな形になるだろう?体の表面にあるのか、それとも内部か、その両方か?もっとも強く感じるのはどこか?逆に最も弱いところは?中心と端の部分とでは感じ方が異なるか?脈動か振動を伴っているだろうか?それは軽いか重いか?動いているか止まっているか?温かいか冷たいか?
・ステップ2 息を吹き込む
感覚の内部や周囲に息を吹き込む。まず何回か深い呼吸をしてみよう(できるだけゆっくりする)。息を吐くとき肺を完全に空っぽにしよう。ゆっくりとした深い呼吸をすることが重要だ。それは体の緊張を緩める。感情を追い払うことはできないが、深い呼吸は体の中に穏やかな中心点を作るだろう。それは感情の嵐の中の錨のようなものだ。錨は嵐を遠ざけることはできないが、それが過ぎ去るまであなたをつなぎ止めてくれる。ゆっくりと深い呼吸をして、息が感覚の周囲や内部に流れ込むのを想像しよう。
・ステップ3 感情の居場所を作ってやる
感覚の内部や周囲に息を吹き込むというのは、体の中にさらなるスペースを作るようなものだ。その感覚の周囲にスペースを作ってやり、それが自由に動き回るための場所を作ってやる(感覚が大きくなるよならさらに大きな場所を作る)。
・ステップ4 容認する
たとえそれが好ましいものでなくても、感覚の存在を容認してやる。別の言い方をすれば「あるがままにさせる」ということだ。あなたの心が起こっていることにコメントをしたら、「心よ、ありがとう!」と伝え、観察に戻ればよい。もちろん簡単ではないだろう。感覚を追い払いたい衝動に駆られるかもしれない。その場合は衝動を承認してやろう。(承認とは、うなずいて存在を認めてやること、「そこにいるのか、見えるよ」と言ってやるようなものだ)。そして、注意を感覚に戻してやる。」(p.126-127)
以上が「拡張」というテクニックです。
このテクニックは、ハリスも再三注意を行っているのですが、感情を消そうとする「コントロール戦略」ではない点には注意が必要です。実際上は、そこまで強くない不安とかだと、深呼吸をしているうちに消えていく、ということは実践者の経験上割とあるようです。私もやっているのですが確かにあります。
しかし、それを「目的」としてしまうと、感情がなくならない場合に、がっかりしたり自分を責めてしまったり、といった、「汚い」不快感を生んでしまいます。ですので、あくまで「受容すること」を目的だと意識するのが大事だとハリスは言っています。
この深呼吸のテクニックはいろいろ応用が利くというか、様々なレベルで微調子が可能です。ここで紹介したものはかなり本格的というか、いつでもここまでやれるわけではないと思います。しかし例えば、ただ深呼吸を二、三回ゆっくり行うだけでも、かなり気持ちを落ち着かせることができるし、やろうと思えばいつでも練習できます。
なので、まずは単純に、普段から意識して深呼吸をしてみる、というのがおすすめです。

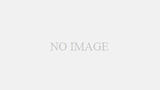
コメント