さて、いよいよ今回から、具体的なテクニックやエクササイズについて書いていきたいと思います。
今回取り上げるのは「脱フュージョン」と呼ばれるテクニックです。
それについて紹介するにあたって、まずは「言語」についての考察をする必要があるのですが、次の引用文を読んでみてください。
「今朝、私はレモンを手に取り、明るい黄色の表皮を指で撫でてみた。一つ一つのくぼみを感じてみる。鼻に近づけて、その芳醇な香りを嗅いでみる。次に、それをまな板に載せて半分にスライスし、その一つを取り上げて、口を開け、舌の上に果汁を一滴垂らしてみる」(p.48)。
どうだろうか?舌に唾が湧き出さないだろうか?私は湧き出ました。しかしこれは冷静に考えると、結構不思議なことではないでしょうか?つまり目の前に、レモンは実際は存在しないわけです。あるのは文字だけです。PCならモニターに映し出された電子的な光、書物ならば紙に印刷されたインクのシミしかない。しかし、言葉の力で、「実際に」そこにレモンがあるかのごとくに、体は反応してしまうということが起こる。
スリラー小説やミステリー小説を読んでドキドキするのも、言葉の持つ力があってのことです。私たちは小説の中の人物が危険な目にあえば、それこそ実際に手に汗を握る。
言語を持っているのは人間だけだと言われます。ほかの動物も、ジェスチャーや表情、様々な音によってコミュニケートはしていますが、厳密な意味での「言語」は持っていません。
ここで言う「言語」とは、「シンボルによる複雑なシステムだ(「シンボル」とはそれ自体とは別のものを表したり言及する何かを指す)。たとえば、dogという言葉は英語では特定の動物を指す。フランス語では同じ動物のことをcienと呼ぶ。イタリア語ではcaneである。三つの異なるシンボルが同じものを指しているのだ。〈改行〉私たちが感知し、感じ、考え、観察し、想像し、交わることのできるものはすべて言葉でシンボル化できる。時間、空間、人生、死、天国、地獄、現実には存在しない場所、最近の出来事、などなど」(p.49)。
そして言語は、その使用場面によって、いくつかの区別を導入することができる。「文書の言葉は「テキスト」、話し言葉は「会話」、頭の中で使用される言葉は「思考」と呼ばれる」(p.49)。
「頭の中で使用される言葉は思考」というのは多少違和感があるかもしれませんね。ここは重要なところなのでもうちょっと説明します。
ハリスによれば、「思考」というのは、頭の中の言葉、のことです。そしてそれは、しばしば思考と同時に発生する、「イメージ(心像)」や「肉体的な感覚」とは区別されるべきだ、とハリスは言います。そしてこの区別を理解するために、簡単な思考実験を持ち出してきます。
「あなたが明日の朝、朝食として作るものについて考えてほしい。次に、それについて考えながら目を閉じ、わき起こってくる考えを観察する。それがどんな形をとっているかよく見てみる。目を閉じて三十秒ほどやってみよう」(p.49)。
さて、これをやってみると、先の三つの区別が腑に落ちるだろう。三つのものが、順番はどうあれ、発生してくるのではないでしょうか。一つは、具体的な「絵」が浮かんだと思う。例えばトーストとか卵とかの。そして料理をしているときのにおいとか、食べた時の味も想像したかもしれない。あとさらに、「俺だったらトーストと卵かなぁ…」といった形で、頭の中でひとりごとをしゃべらないだろうか?
で、まあ一般的には、これら三つをすべて含めて、心の働きというか、広い意味での「頭の中での考え」としているのだと思うんだけど、この本においては、それぞれ別の対応をする必要がある、ということからも、あえてはっきりと区別して扱う。
思考=頭の中の言葉
イメージ=頭に浮かぶ絵
感覚=体の中に起こる感じ
(p.50)
そして特に、頭の中の言葉としての「思考」が人間にとっては大きな存在だという。
「人間は思考に大きく依存している。思考は私たちの人生について、またそれをどう生きるかについて教えてくれる。私たちがどのような存在であり、そしてどのような存在であるべきか、いかに行動し、何を避けるべきかも教えてくれる。だが、思考はあくまで言葉でしかない。このため、ACTではしばしば「思考」を「物語」と呼ぶ。これらの物語は、時に真実だが時に間違っている。しかしほとんどの場合、思考は真実でも間違いでもない。ほとんどの思考は私たちの人生の見方(意見、態度、判断、理想、信条、見解、道徳観など)の物語か、人生で何をしたいか(計画、戦略、目標、希望、価値観、その他)の物語かのどちらかだ。ACTでは思考が真実かどうかは重視しない。それが助けになるかどうかに重きを置く。つまり、私たちが注意を向ける考えが、望む人生へのプラスになるかどうかが大切なのだ」(p.50-51)。
そしてそれが「物語」であるということは、「実際の出来事」とは別の存在だ、ということだ。
例えば、ある銀行で強盗事件が発生したとする。翌日に新聞記事になる。どの新聞かによって、内容の正確さが違うだろう。目線の置き方、立場の違いもあるだろう。いずれにせよ共通しているのは、当たり前だが、それらの記事は出来事そのものではなく、それを言語で表現した物語だ、ということだ。「実際の出来事」を経験したと言っていいのは、その場にいた目撃者だけだ。その人が体験しているものそのものが「実際の出来事」だ。そしてそれは後にその人が語る「物語」とも違う別の何か、だ。
で、新聞の記事に書かれている「物語」を読むかどうかは私たちの意志に任されている。つまりいつでも読むのをやめることができる。参考にするのも無視するのも自由です。しかしこれが頭の中の物語だとしたらどうか?しかもそれは客観的な出来事の記述とかではなく、自分に対する評価の物語、しかも非常にネガティブな物語だとしたら。「俺はクソだ」とか「人生の敗残者だ」とかそういった。
そういった思考が発生するだけで、脊髄反射のように、嫌な気持ちになるだろう。憂鬱になってくるだろう。それはなぜと言って、それらの評価の言葉を、距離をとって物語として理解しているのではなく、人生経験を元にして導き出した「真実」「事実」として扱ってしまうからだ。
このように、思考と事実を区別せず同じ塊として受け取ってしまうことを、この本では「フュージョン」と呼んでいる。「フュージョン」ということで、金属二枚を溶かして混ぜてしまうような状態を表現している。つまり単なる「合体」ではなく、「融合」ともいうべき、混合を指している。合体、というのはロボットアニメにおけるそれがそうであるように、部分部分は独立を保ったまま接合部によってつながる状態、「ドッキング」のことだろう。それに対して融合というのは、例えば合金においてその部分をなす片方だけの金属をすぐに取り出すことはできないような混じり合いのことだ。
「ACTにおけるフュージョンは、思考と、それが指し示すもの(物語と実際の出来事)が混じり合い一つになった状態を指す。私たちはレモンについての文章を読み、本当にレモンがあるかのような反応を示す。犯罪小説を読んで、本当に誰かが殺されるかのように反応する。「自分は無能だ」という言葉には、本当に無能であるかのような反応を示してしまうのだ。「私は失敗する」という言葉にも、それが避けられない結末であるかのように考えてしまう」(p.52)。
思考と「フュージョン」していると、私たちはその思考を、実際に目の前で起こっている現実と考えてしまう。そしてそれは事実としてとらえられているのだから、私たちはそれと真剣に向き合い、その思考に沿って行動を組織する。その思考に対する疑いがさしはさまれる余地はない。
ハリスは、思考とのフュージョン一般が悪いものだとは言っていない。むしろ人の心の機能として当然のことだし、思考に従って行動するのは当たり前で、必要なことでさえある、という。しかし問題になる場合が多いのは、自己に対するネガティブな評価の場合だ。
「俺は無能」「俺はクソだ」「人に嫌われている」「元ひきで人生詰んでる」とか。これらの思考は、私の人生をより良い方向に向かわせようとする際に、何か役に立つだろうか?過去の失敗から、この先の行動のために何か学べることを引き出すよう反省するのは有益かもしれない。しかし実際のところ、それをやれる人はどれだけいるだろうか?実際は、上のような言葉は、自分で自分をただいじめているだけであり、やる気をそぎ、ひどい場合には鬱へと導くことしかしないのではないだろうか?
さて、ここでいよいよ具体的なテクニックを紹介します。それは「脱フュージョン」というテクニックです。
テクニックは三つ紹介されている。ハリスは、テクニックを「自転車の補助輪」に例えている。「ACTでは脱フュージョンのためのテクニックをたくさん用意している。いくつかはあざとい仕掛けに見えるかもしれないが、喩えて言えば自転車の補助輪のようなものだ。一度乗り方を覚えればそれらは必要ない」(p.55)。
最初に紹介されているテクニックは、こういうものだ。「私は…だ」という思考に対し、それを、「私は「自分が…だ」という考えを持っている」という文章に入れてみよう、という非常にシンプルなものだ。
例えば、先の私の例で言えば、私はちょくちょく、「俺はクソだ」とか思ってしまう。仕事中に失敗したり、他人をイライラさせてしまったときに、脊髄反射で脳内に浮かぶ。最終的にはその現場でできることが理想だが、練習は家で落ち着いてできる。家の中でも、「俺はクソだ」と考えてしまうと気持ちが沈み込む。そこで、まずはあえてその言葉を思い出して、気持ちの変化を観察する。そしてそのあとに、「俺はクソだ」とただ考えるのではなく、「俺は今、「自分はクソだ」という考えを持った」と頭の中で呟いてみるのだ。
これを実験してみると、「俺はクソだ」という考えに対して、距離をとれるようになる。それがある特定の「考え」であり、単なる言葉の羅列であると思えるようになる。そしてその思考と密着せず、客観的な対象として見れるようになる。
これを繰り返し練習していると、普段から、例えば仕事中のネガティブな思考に対しても距離をとれるようになる。
しかしここで注意が必要なのは、これは「コントロール戦略」ではない、ということだ。つまり、自分の心をコントロールして、ネガティブ思考を完全に発生させないようにする訓練とは違う。ハリスの根本的な立場は、先に述べておいたように、そもそも人の心は、進化の果てにネガティブに考えるようにできている、というものだ。ネガティブ思考をすべて根絶やしにしようとすることは、自分の人間性そのものに挑戦することに等しい、というのだ。私たちにできるのは、ネガティブに考えることをやめることではなく、可能な限りネガティブ思考のデメリットを少なくすることだ。
「脱フュージョン」の方法の二つ目は、先のネガティブ思考が頭の中に浮かんでしまった際に、その文章をメロディに乗せる、というものだ。これなどは確かに、ハリスの言うように「あざとい仕掛け」に感じてしまうかもしれない。私もこれはあまり実践しなかった。「ハッピーバースデー」とか「ジングルベル」のメロディに乗せて、「おーれはー、くーそだー♪」ってな感じで頭の中で歌う、という(笑)。まあ確かに自分でも笑っちゃう感じで、思考に対して距離は取れる。しかし日常でずっと繰り返し使うには何となく私は合わない感じでした。
ただここら辺は、ハリスも強調しているのですが、ACTは宗教的な儀式のようなもの、必ずこれをやれ!というものではないのだそうです。自分に合ったものを選んで、気に入ったものがあればそれだけやり続けてもいい、と。
で、三つ目のが、物語に名前を付ける、という方法です。先に書いたように、私の場合も、よく出てくる物語というものは決まっている。「俺はクソだ」とか「俺は無能だ」とか。そしたら、「俺はクソだ」の物語だ、と名付けてしまって、その思考が出てきたら、「また「俺はクソだ」の物語だな…」と客観化し距離をとることができます。
さて、以上が思考に対する「脱フュージョン」のテクニックです。実際にやってみること、が大事なのだそうです。一つ一つのテクニックはシンプルで今すぐにでも試せるものですので、興味を持った方は、ぜひ実践してみてください。

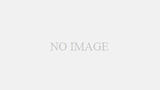
コメント