ストイック暗記王の後編の放送を観ました。前回は、ぱーてぃちゃんのすがちゃんと品庄。今週のはトムブラウンとラブレターズ。ラストのラブレターズのが、「スクールカースト3.5軍」ネタの大作でしたね。
ラブレターズ塚本さんとうるとらブギーズ佐々木さんは、中学校の同級生だそうです。「マジ歌選手権」で佐々木さんが「3.5軍」という曲を披露しています。二人は、いじめられるなか、親友となり、お互いに芸人になるという夢を抱いていたそうです。
で、ストイック暗記王のネタは、学生時代の設定です。実際の世界とは異なる世界線で、佐々木さんは「3.5軍」としていじめられているのだが、塚本さんは「1軍」である、という設定。佐々木さんは、いじめっ子から、「夢である芸人にはなれっこない」と口に出して言うよう強要される。で、そこで「1軍」である塚本さんが登場!「なれるよ!」と叫ぶ胸熱な展開の、見てる方も本気で泣いちゃうパターンのやつ(笑)。
で、私も感動して観ていたものの、次の瞬間ハッとして、自分には「親友」もいなけりゃ、あいつらを見返せるような人生も送ってないな…、ってなことを考えてしまいました。
いや、いつまで我々はスクールカーストに振り回されるんでしょうね…(笑)。まさに、漫画家の山田玲司さんの言う「スクールカースト後遺症」ですね…。もはや教室の中にはいないってのに。誰かのつぶやいた「きもっ…」っていう言葉のとげがいまだに心臓に刺さってて、時々チクチク痛むわけです。
で、塚本さんも佐々木さんは本当に立派だ…。見事にあいつらを見返した、んだと思う。そして二人の友情は美しいし、素直にうらやましい。
とはいえ、自分の状況をかえりみるに、ちょっと「うっ」となってしまった。
で、「スクールカースト」再考、とあいなりました。
んー…。スクールカースト的なものに対する戦い方というか、対応の仕方としては、二つの戦略があるでしょう。つまりそのゲームを認めた上での対応と、そのゲームそのものの廃棄、と。
まず単純にそのスクールカーストでの上昇を目指す、というのがストレートな対応。しかしながら、そもそもそういった「上昇」が考えにくい序列こそが、「スクールカースト」の特徴ではある。(『教室内カースト』光文社新書 鈴木翔著)
で、塚本さんのように別のゲームでの勝者となり「見返す」という復讐戦略がありえます。
しかしながら、そもそもの「スクールカースト」的なゲームの廃棄、というか、そもそものあらゆる「勝敗」のゲームの拒否、を夢想してしまうのは、どうあっても「勝てない」最弱者のルサンチマンからくる夢想なのでしょうが、夢想せずにはいられません。
で、「夢想」の夢想たるゆえんというか、具体的な形は思い浮かばないのですが。それに例えば、「スクールカースト」的なものの恐ろしさというか強さは、外部を持たない点というか、常に外側を取り込んでくる力があるというか。
つまり例えば、経済的には貧しくても好きなことをやって満足して生きる、というような「社会的な勝ち負け」とは別のルールで生きようとしても、社会の方が「お前は負け組だ!」と押し付けてくるというか…。
いや、この場合でも実は問題は「自意識」なのかもしれませんね。つまり「お前は負け組だ!」と言っているのは社会ではなくて自分自身の心なのでしょう。(別の投稿で取り上げた「心理療法のACT」を参照)
できることと言えば、深呼吸して、過去のスクールカーストから、意識を「今ここ」の感覚へと振り向けることくらいでしょうか。今ここ、で呼吸しているこの身体こそが、スクールカースト的な社会的圧力の外部になりうるか、少なくともその脱出口にはなるのではないでしょうか。

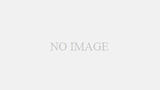
コメント